2018-10-19 (Fri)
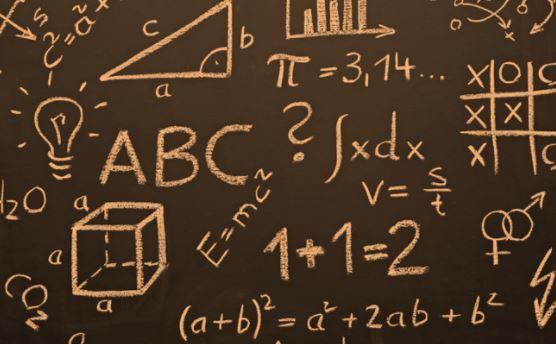
定義(ていぎ)は、一般にコミュニケーションを円滑に行うために、ある言葉の正確な意味や用法について、人々の間で共通認識を抱くために行われる作業。一般的にそれは「○○とは・・・・・である」という言い換えの形で行われる。基本的に定義が決められる場合は1つである。これは、複数の場合、矛盾が生じるからである。
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 「頼む! 一生のお願い」
この言葉を聞くのは、いったい何度目だろう。福山翔太は、わざとうんざりした表情を松本堅、通称マツケンに向けた。桜が散り始める4月初旬、翔太とマツケンはお互い仕事を終え、居酒屋でちょうど一杯目を空けたところだ。

翔太とマツケンは県立青陽高校の同級生。10年前に卒業し、いまも年に数回は会って酒を酌み交わす仲だ。…
マツケンの父親は青陽高校のOB・OG会の幹部で、年に一回、卒業生を講師に招いて生徒向けの講演会を開催している。時期は5月の連休明け。今年はホテルマンとして活躍している息子の親友に白羽の矢が立ったということらしい。翔太は大学卒業と同時に、全国展開している有名ビジネスホテルチェーンに就職。主にフロント業務を担当している。…
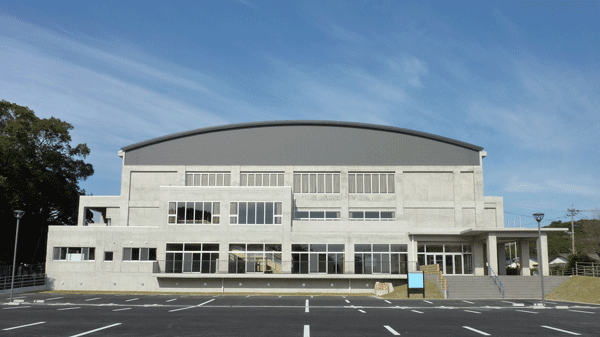
名前を紹介された翔太は、後輩たちの拍手の中、壇上に上がった。青陽高校の体育館。800名弱の後輩たちは思い思いの格好でパイプ椅子に腰かけ、「基本、期待していませんから」といった表情でこちらを見つめている。普通の人なら緊張で足が震えるのだろう。しかし翔太はむしろこの状況を「うお、みんな俺見てる。ヤベえなこれ」と楽しむ余裕があった。
マツケンの「一生のお願い」からおよそ1ヶ月、講演で何を話そうか、それなりに真剣に考えてきた。彼らより先に経験したことを、どう自分なりの味つけで伝えるか。考えたシナリオは、我ながら完璧だ。いよいよ始まる。簡単な挨拶のあと、翔太はおもむろに口を開いた。
「僕は、あなたたちの年齢の頃、父を病気で亡くしました」
体育館の空気が変わる。狙い通りだ。翔太は話を続ける。

翔太の父親は、車の部品を製造する中小企業の経営者だった。もともと【理系出身】で、技術の世界で戦い、38歳で起業。翔太が10歳の時だ。その後事業は順調に成長するも、ライバル企業との熾烈な競争に負け、従業員の退職なども重なり窮地に追い込まれた父は、誰よりも自分を責めた。そして脳梗塞であっけなくこの世を去った。翔太が18歳の時だ。
「自分を責め続けた父は、幸せだったんだろうか……と、強く思うんです」
後輩たちは真剣な眼差しで聞き入っている。オープニングトークはここまでだ。さあ、ここからは楽しくいこう。
「僕は、父親を尊敬しています。でも自分が父親と違うところを一つ挙げるとするなら、ある意味で"テキトーさがある"ということだと思っています。先のことなんて考えても仕方ありません。いくら考えたって、なるようにしかならない。結局、人生は楽しく生きるのが一番。その瞬間瞬間に、したいことをしたらいいんじゃないかと思います」
そこから笑いも交え、大いに盛り上がった講演内容は要約すると、次のようなものだった。
◯ やっぱり【友達は多い方がいい】(僕のように)
◯ 日本で普通に働いていれば、【お金に困ることなんてない】。【お金を使わないこと】が【カッコいい時代になる】(僕のように)
◯ 【仕事】も同じ。高望みせず【普通にやっていればどうにかなる】(僕のように)
◯ 真面目な人ほどバカをみる。【要領よくやる人がうまくいく】(僕のように)
◯ 仕事だけじゃ人生つまらない。【恋愛】もどんどんしよう(僕のように)
◯ 【将来役に立たない学問はしない方が賢い】(僕のように)
オッサンたちの好む精神論や、自称評論家がテレビで言いそうな「べき」論。そんなもの誰も聞きたくない。それより、自分のような「イケてる」20代のリアルな生きざまの方がいまの学生には伝わる。そう確信していた翔太は、得意のパフォーマンスも交え、見事にさわやかな大人を演じきった。講演の終了後、翔太の前にはLINE交換の列ができた。翔太は仕事では味わえない充実感を得て、有頂天になっていた。』

いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、「数学」的に物事を考えるということが、私たちが日々暮らしている中で、いかに意味あることなのか、を非常に分かりやすい小説の形で表現されている良書となります。あまりの面白さに、ついつい引き込まれてしまって、あっという間に読み終わってしまいました。お話の最後のところも、良かったと思います。ぜひ、御一読してみてください。

さて、このあとのお話は、実際に本書を御覧頂きたいと思うのですが(ネタバレだと詰まらなくなってしまいますので)、おおまかな流れは、翔太の講演の中にあった、6つの要点について、「数学」的に物事を考えていく、という構成になっています。
つまり、
【命題①】 「友達」は多い方がいい。
【命題②】 「お金」に困る心配はない。
【命題③】 「仕事」で困る心配はない。
【命題④】 「真面目」だけではなく「要領」も必要である。
【命題⑤】 「恋愛」することはメリットをもたらす。
【命題⑥】 「数学」は学ぶ必要がない。
という命題について、それぞれの言葉の定義を行った上で、「数学」的に思考を巡らせて、主人公とヒロインの2人が「お互いが納得できる答え」を見つけていく(←ここが非常に重要なところです)、という小説です。

ここで、「数学」的に思考を巡らせるということが、どういうことなのかと申し上げますと、
【命題①】 「友達」は多い方がいい。
という「命題」が、いま私たちの目の前にあるわけですが、
「友達」って何でしょうか?
というところから始まるのですが、それを面倒くさいって考えるのが「文系アタマ」の思考方法になります💛

つまり、「文系アタマ」は、「友達」は、
「(俺が知っている・認識している)友達だろ!」
とか
「そんなの(私が知っている・認識している)友達以外に何があるっていうの?」
って思考します(笑)

先日も書かせて頂きましたが、
【問題】 いま、「地球上のすべての人々は、理想社会の実現を目指している」、とします。あなたが描く状況は、次のどちらが「正しい」でしょうか?
① それぞれ各自が、独自の理想社会のイメージを持っている
② 地球上のすべての人々は共通して、ある理想社会のイメージを持っている
という問題の答えは、「どちらでもあるといえる」のですが、
詳しくはこちらをご参照💛
↓
☆柴犬と、文系アタマと、指示待ち族
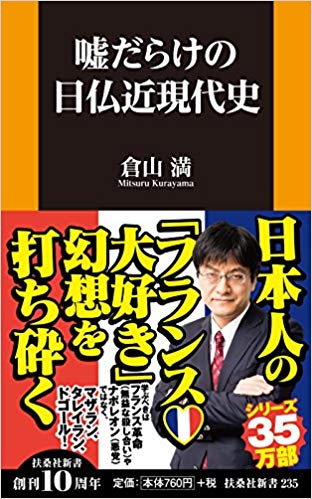
そういった問題が生じてしまう理由が、キチンと「言葉」を「定義」していないからになります。
「数学」的に思考することが大切なのは、自分自身で「答えはこうである」と納得できるということはもちろん、たとえ異なった意見を持った方々であったとしても、何とか「お互いが納得できる答え」を見つけていく、ということが可能になる、というところにあります。
ですから、議論の前提となる「言葉」の「定義」は非常に重要であり、それを勝手気ままに自分なりの考え方のみで「好き勝手」に決めておいて、「ああだこうだ」とぬかしているものは、単に笑い飛ばしてさしあげれば良いものでしかない、ということになります💛

詳しくはこちらをご参照💛
↓
☆とうとう「嫌われ恐怖症」に陥った朝日新聞

で、そのため(→何とか「お互いが納得できる答え」を見つけていく)にも、
【命題①】 「友達」は多い方がいい。
という「命題」が、いま私たちの目の前にあると致しまして、
「友達」って何でしょうか?
というところから始まり、
それが「多い」とか「少ない」とかを、どのように判断するのでしょうか?
そして、
「いい」というのは、どういう意味なんでしょうか?
さらに、
はたして、【命題①】は真であるのでしょうか?
って、考えていく必要があるわけです💛

そういった能力が無い連中のことを「左翼リベラル」とも言います(笑)

さて、それではここで、「数学」的に思考するための大前提となる「数学」について、御一緒に考えてみましょう💛
そもそも「数学」って、何でしょうか?

大丈夫ですか?
固まってしまっていませんか💛

恐らく、多くの方々は、この質問に即答することができない、つまり「数学が何かということを知らない」、のではないかと思われるのですが、その一方で、「数学を知っているはずだ」、と思う御自身がいらっしゃる、のではないでしょうか?
つまり、「知らない」けど「知っている」という明らかに「矛盾」する状態にある、のではないでしょうか?

だったら、この際、「数学」が何かということを知らない、という前提で、これから御一緒に考えていきませんか?
その方が、「ウソ」をつかなくても良いですし、お気楽ですから💛

ということで、私たちは「数学」というものが何であるのかを、まったく知らない、単なる「バカ」であり「アホ」だと致しましょう(笑)
ただし、直感的に「足し算」と言うものは理解していて、また「九九」を覚えさせられた(=丸暗記)ため、「掛け算」というものも理解している、という前提で考えていきたいと思います。
ですので、「引き算」とか「割り算」については、まるっきり理解が出来ない、単なる「バカ」であり「アホ」、というのが「私たち」になります。

そんな私たちの目の前に、ひとつの「箱」があります。

どういう訳でそうなっているのかは、まったく知らない(何しろ、「バカ」であり「アホ」なのですから)のですが、何故か、この「箱」に、ある「数字」を放り込むと、「何らかの数字」が飛び出してくるそうです💛

この「箱」のことを「数学」では、「関数(函数)」と呼ばれているそうですが、そんなことを私たちは、まだまだ知りません。
ですので、
「関数(函数)」って、何でしょうか?
「関」と「函」って、何が違うのでしょうか?
と考えなければなりません。
そうです💛 これこそが、「数学」的な思考になります。

続きは次回に♥
ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥
↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事
-
- ハチやアリは、集団の意思を決定するときに多数決を使っています (2018/11/09)
- 神であるヤハウェ(ヤハヴェ、エホバ)を信仰しても無駄であるという典型的事例 ~ エホバの証人 (2018/11/08)
- 高校でも大学でも、進化の原理についてほとんど教えられることはない、という現実 (2018/11/07)
- ポティファルの妻に濡れ衣を着せられたヨセフ ~ 安田純平に濡れ衣を着せられた武装勢力 (2018/11/06)
- 相手がその言葉で何を意味しているのか。。。を考えることの大切さ (2018/10/29)
- 数学的な考え方 ~ 結論だけではなく、「仮定」も、その両方ともが重要です (2018/10/26)
- 日本は借金だらけ、と考えてしまう、困ったアタマの方々が「文系アタマ」です(笑) (2018/10/25)
- 友達は多い方がいい、というのは本当でしょうか? (2018/10/19)
- 【連想ゲーム】 ユニコーンとユニオンと関西生コンと西早稲田 (2018/10/18)
- 前川喜平と「御器かぶり」 (2018/10/08)
- キリスト教に改宗した「ルーシ・カガン」 VS ユダヤ教に改宗した「ハザール・カガン」 (2018/10/02)
- テレビを見ると「脳」が破壊されてしまう理由 (2018/10/01)
- 池上彰等の本を読むというのは「読書」ではなく「毒書」です(笑) (2018/09/30)
- 【問題 】 世界初の地下鉄の開通はイギリスのロンドンですが、それでは、2番目と3番目は、一体どこの国の何という都市でしょうか? (2018/09/26)
- 「シルクロード」を支配した国の初代王者「ソンツェン・ガンポ」 (2018/09/25)
