2019-08-13 (Tue)

本日のキーワード : 法定貨幣
紙幣(しへい)とは、紙製の通貨の事である。
紙幣(しへい)には、政府の発行する政府紙幣(Print money)と銀行(中央銀行など)の発行する銀行券(Bank note)があるが、特定地域だけで通用する地域紙幣(地域通貨)が発行されることもある。現在の多くの国では中央銀行の発行する銀行券が一般的であるが、シンガポールなど政府紙幣を発行している国もある。現在多くの先進国の中央銀行が完全な国家機関ではなく、民間企業の投資などで出来ていることから、中央銀行のありかたを疑問視する考え方が最近世界中で起きている。そのため代替案としての政府紙幣、地域通貨なども再び脚光を浴びはじめている。
現在の日本では、政府紙幣は存在しないが、日本銀行が開業するまでは政府紙幣が発行されたほか、大正時代や昭和時代には小額銀貨の代用としての銭単位の低額の政府紙幣が発行されたこともある。法令用語としての「紙幣」はもっぱら政府紙幣を指し、銀行券は含まないが、日常用語としては、日本銀行券を指して紙幣と呼ぶ。

1938年(昭和13年)の富士桜50銭券(政府紙幣)
本日の書物 : 『日本史に学ぶマネーの論理』 飯田泰之 PHP研究所
戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。
そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。
私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、
客観的に情勢を判断する必要があります。
それでは、この書物を見ていきましょう!
『 ここで登場するのが貨幣誕生に関するもうひとつの神話、【貨幣法制説】である。ごく簡単にまとめるならば、皇帝や貴族、時の政権が【「これが貨幣である」と宣言したものが貨幣になるという考え方】だ。
もちろん、何の根拠もなしに宣言したのみで、ある商品や金属片が貨幣として社会に受け入れられるということはない。そこには【なんらかの裏付けが必要】である。そして、政府が貨幣を貨幣として流通させるためには、その【価値の根拠を社会に対して示し続ける努力が必要となる】だろう。例えば、官位を得るためには一定以上の銭を保有している必要があるとした蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)はそのひとつの工夫と言えよう。
法律や命令によって生み出される貨幣――【法定貨幣】にとって【最も直接的な価値の裏付け】となり得るのは【「それによって税金を支払うことができる」こと】だ。政府がある対象(例えば和同開珎)を「これが貨幣である」と身をもって示すには、政府への支払いに和同開珎を用いてよいと認めることが近道となる。

そもそも政府に対する支払いに用いることができないものを「政府が公的に貨幣であると定める」というのはあまりにも矛盾した姿勢である。これこそが、納税やそのほかの政府に対する支払いとリンクしていなかった富本銭の流通に限界があった理由かもしれない。

富本銭(複製品)
政府が自らが発行した貨幣を政府自身への支払い方法として認めると言うとき、その【法定貨幣は重要な性質を持つことになる】。【それが「政府負債」という性質であり、現代的に言うならば国債に類似した性質】だ。

現代社会に生きる私たちにとって、【1万円札】と【国債】は【全く別物のように感じられる】。例えば、来年度の日本国政府が税収の裏付けなしに100億円の支出を行おうとする場合を考えてみよう。

政府は100億円の【国債を発行し、これを民間に売却】する。この【借入】によって民間から100億円の貨幣を手に入れた政府は、それを使って社会保障給付や公共事業を行う。発行された【国債はのちに税収の一部を用いて返済されていく】ことになるだろう。このとき、【国債が政府の負債である】ことを理解することはむつかしいことではない(むしろ当然すぎる)。
一方で、政府が直接的に【1万円札を印刷して支出】を行ったとしたならばどうだろう。これを【債務であると認識する】ことは少々むつかしいかもしれない。
1万円札には返済期限が設定されていない。そして、1万円札の所有者が政府機関や日本銀行に1万円札を持参して「金をかえしてくれ(?)」と迫ったとしても、渡されるのはせいぜい新品の1万円札であろう。ここから、私たちはともすると【現金やベースマネー(現金と民間銀行の日銀への預金)の負債性・債務性】を見逃してしまう。

しかし、【現代の貨幣】もまた【「将来それで税金を納めることができる」】という意味で【政府にとっての負債】であり、【民間にとっての資産】である。

企業会計においても、自社が発行した商品券がその会社にとっての負債であることを思い出されたい。貨幣の負債性を認識しにくくなる大きな理由は、現代では税金を貨幣で納める以外の状況を想像しづらいところにある。…

【政府負債】が【直接的な納税手段以外の用途を持たない状況】では、【その発行は大きな貨幣発行益は生まない】。極端な例だが、政府からの支払いとして得た銭をその日のうちに納税に使ってしまう状況を想像されたい。【貨幣発行益】は【政府が発行した負債】が、すぐには、または半永久的に【税金の支払いに向かわない状況になったときに生まれる】。これは、【政府負債(の一部)が税金支払い以外の用途――典型的には貯蓄の手段、取引の支払いツールとして用いられるようになることで発生する】。』

政府にとっての負債、民間にとっての資産
いかがでしょうか?
今回ご紹介させていただく書物は、我が国の歴史である国史の流れの中の「おカネ(貨幣)」に注目し、そこから現代経済学の知見に基づいて検証し、「経済」と「金融」というものを改めて考えていくというテーマで書かれた書物であり、「おカネ(貨幣)」というものが、そもそも何であるのか、ということを理解できるようになる良書になります。

さて、政府が「名目貨幣」(原材料価値を上回る価値を持って流通する貨幣)を発行し、それによって原材料価値を上回る財・サービスを購入することによって生まれる利益、これを「貨幣発行益(シニョリッジ、通貨発行益)」と呼びますが、それは同時に物価が上昇する(インフレーション、インフレ)ことで、貨幣を貯蓄している者にとっての負担でもあるため、貨幣を持つ者全てから徴収することができ、尚且つ、より多く貯蓄している者により多くの負担を求めることができる(累進課税のような役割)という意味において、「インフレ税」と言えるものでもあります。
そして、本文中に書かれていたように、その「貨幣発行益」は政府への「税金」の支払いに向かわない状態であればあるほど、生み出されるものになります。

本書で示されている「実質的な貨幣発行益」は、次のような式で表されています。
実質的な貨幣発行益
= (新たに発行した銭で購入できる財・サービスの量)
+ 物価上昇率 × (すでに発行している銭の量)
- 鋳造費用
ここで、上の式の赤文字の部分は何を意味しているのでしょうか?

私たちが用いている「おカネ(貨幣)」も、「政府の負債」であり「民間の資産」であるという表裏一体の関係にあります。
ですので、民間の側からすると、
物価上昇率 × (すでに発行している銭の量)
= 物価上昇率 × (民間の資産の量)
であり、政府の側からすると、
物価上昇率 × (すでに発行している銭の量)
= 物価上昇率 × (政府の負債の量)
と置き換えることができます。
いま仮に、物価上昇率が10%であったと致しますと、民間の側からすると、1つ1万円だったものが、10%値上がりし1つ1万1千円になったため、手元の100万円で100個買えたのが、約91個(=90.909090・・・)しか買えなくなってしまうということになります。ですから、民間の側からすると、
物価上昇率 × (民間の資産の量)
で計算される分だけ目減りすることになります。
他方、政府の側からすると、「民間の資産」の目減りは、「政府の負債」の目減りでもあるわけですから、政府側から見た「実質的な貨幣発行益」にプラスに作用することになります。
つまり、「おカネ(貨幣)」の供給量を増やすことで、「民間の資産」が政府側に移転するという現象が起こるということです。

さらに、政府の側から見た場合、同様の効果をもたらす、もう一つ重要な手段があります。それが、国民から与えられる唯一無二の特権である「徴税権」です。「政府の負債」である「おカネ(貨幣)」を「徴税」というシステムで回収し相殺する方法です。

本書で示されている「民間部門の純資産」と「政府部門の純資産」は、次のような式で表されています(※簡易化のための前提として、政府は実物資産を持たない、海外との取引も考慮しない)。
民間部門の純資産 = 実物資産 + 政府負債 - 徴税権負債
政府部門の純資産 = 徴税権資産 - 政府負債
ここで、「おカネ(貨幣)」は、「政府の負債」であり「民間の資産」であるという表裏一体の関係にありますので、「民間部門の純資産」と「政府部門の純資産」とを足し合わせたとき、つまり、「一国の純資産」を考えた場合、それらは相殺されることになります。

すると、次のような式で表すことができます。
一国の純資産 = 実物資産 - (徴税権負債 - 徴税権資産)
で、ここで注意しなければならない点が、民間にとっての「徴税権負債」と、政府にとっての「徴税権資産」とは、非対称性があるという点です。
「徴税権負債」は「納税額の割引現在価値」で、また「徴税権資産」は「徴税額の割引現在価値」となりますが、前者は将来にわたり永久に続くであろうと考えられる負債である一方で、後者はその時々の政権や権力者の支配が続く期間に限定される資産で、従って、民間の「徴税権負債」は政府の「徴税権資産」よりも大きくなります。
一国の純資産 = 実物資産 - (徴税権負債 - 徴税権資産)
そう致しますと、消費税率を8%から10%へと無理矢理引き上げようとする政策は、「(徴税権負債 - 徴税権資産)」の部分を拡大させることとなりますので、我が国の純資産を減少させる方向へと作用することになります。その犯人の一人が、これです。


岡本薫明(おかもと しげあき)


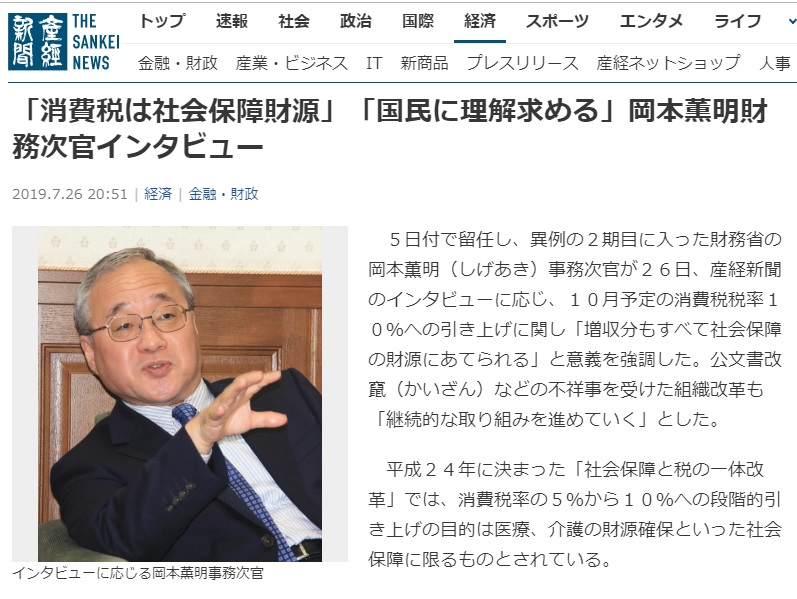
☆「消費税は社会保障財源」「国民に理解求める」岡本薫明財務次官インタビュー

それでは、本日はここまでとさせて頂きますが、最後に一つクイズを出させて頂きます。
(問) 所得税(税率20%)と消費税(税率20%)のどちらか一方の税だけを課税方法として選択することが可能である場合、どちらを選ぶべきか。

続きは次回に♥
ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥
↓↓↓↓↓↓↓
にほんブログ村

人気ブログランキング


- 関連記事
-
- 「おカネ」と「暴力」が表裏一体となる理由 ~ それは、「おカネ」が「政府の借金(負債)」だから (2019/08/23)
- 「日本のメディア」や「Wikipedia」なんかよりも、「読書」の方が圧倒的に「学ぶ」ための近道です (2019/08/22)
- バチカン銀行と暗黒街 (2019/08/21)
- ネオ・クラシカルとニュー・クラシカルとケインズ経済学 (2019/08/20)
- タックスヘイブンとシティ・オブ・ロンドンの金融治外法権 (2019/08/19)
- 日本の“御用”経済学者がノーベル経済学賞を一度も受賞できない理由 (2019/08/15)
- 財務省御用達の経済学者とガラパゴス (2019/08/14)
- 1万円札の正体は? ~ 政府の負債と民間の資産 (2019/08/13)
- 公務員に過ぎない「官僚」は景気変動に対しては、“異常”なほど“鈍感”なんです (2019/08/12)
- 日本の名目貨幣の誕生 (2019/08/11)
- 中国・朝鮮半島よりも遥かに早かった「日本のおカネ」の誕生 (2019/08/10)
- 日本銀行の責任逃れの屁理屈 = 真正手形主義 (2019/08/09)
- 消費税増税なんかしなくても、「財務省が主導する税金の無駄遣い」を無くせば良いんです (2019/08/08)
- 江戸時代のリフレ派 荻原重秀 (2019/08/01)
- 財務省官僚と新井白石の共通点 ~ 経済学誕生以前の古臭い考え方 (2019/07/31)
